面白いことを突き詰める──建設業界のニッチを攻めるオリテック21の独自性と代表・櫻岡氏の想い
written by ダシマス編集部

株式会社オリテック21

岩手県に拠点を置き、橋梁の補修・調査を専門に行うオリテック21。同社の大きな特徴は“ニッチ”であること。その特殊性を理由に、工事車両メーカーから商品開発のためのヒアリングを受けることもよくあります。2025年5月には、かねてからの要望が叶い、日本に一台しかない特殊車両の導入も実現。特許も取得している独自の橋梁用排水パイプの施工をはじめ、他社にはない技術にますます磨きをかけています。
今回は代表取締役の櫻岡賢拓(さくらおか たかひろ)さんに、オリテック21の独自性、そしてその背景にある、櫻岡さん自身の想いを伺いました。

代表取締役 櫻岡 賢拓(さくらおか たかひろ)さん
建設関連コンサルタント業及び建設業を経験をしたのち、2015年7月に(株)オリテック21に入社。2021年6月(当時45歳)に代表取締役に就任。
他社と被らない領域で勝負する。オリテック21の事業戦略
――まず、オリテック21の事業内容を教えてください。
橋梁の修繕工事を手掛けています。とは言っても、当社で橋ひとつの工事をすべて担当しているわけではありません。道路と橋のクッション材的な役目を果たしている伸縮装置をはじめとする、自社の得意領域だけを施工しているのが当社の特徴のひとつです。
部分施工に集中することで材料在庫を最小限に抑え、技術力を強みとして高い利益を出すことができています。
「橋の工事だけなら誰でもできてしまう」「誰もやっていない仕事の方が儲かるはず」そう考えて、点検・調査から工事まで行う唯一無二の会社を目指してきました。その取り組みが創業20年、僕の入社10年を前にして、ようやく花開いたような気持ちで、とてもうれしく感じています。
――創業から20年の間に、少しずつ今の形になってきたんですね。そもそも、なぜ橋梁工事を手掛けることとなったのでしょうか。
当社は、会長の及川謙二が創業した会社です。及川はオリテック21の創業前、コンクリート関連の建設工事などを行うオリエンタル白石にて、盛岡支店の支店長をしていました。その頃、橋梁工事にも関わっていたようです。そして早期退職をし、オリテック21を立ち上げたんですね。
実は当時の及川は橋に関わる事業をするつもりはなく、光触媒などのまったく違う領域に取り組んでいました。しかしうまく軌道に乗らず、もともと携わっていた橋の工事に立ち返ることに。そしてその後、僕のような橋に携わってきた技術者が次々と参画し、今のオリテック21ができていきました。
近年、地方の人口が減少しているなか、数年以内に消滅することが予想されているような集落にある橋は、補修工事をしないという判断が下されることも珍しくありません。
こうして今あるものが失われていっている中で、すでにあるものを直して残していく仕事をしていること。ここに当社の社会的意義があると思います。

――先ほど利益に関するお話もありましたが、貴社の強みはどのような点だと捉えられていますか。
特許を取得している橋梁用の排水パイプだったり、コンクリートを斫る技術だったり、工事の質の高さには自信があります。
また、オリテック21ではないとできないことがあるのも大きな強みだと捉えています。
直近の例で言うと、日本に一台しかない車両を5月10日から導入したんです。橋には、桁と呼ばれる、橋の胴体を支える脚のような部分があります。これまでは、桁の高さが2.5m以上あると、高くて触れなかったんですね。しかし、その車両があれば、3.5mの高さのものまで触ることができる。桁が高い橋でも、実際に手で触りながら作業できるようになるわけです。
このくらいニッチで、他社にはできない工事を行っていることが、オリテックス21の強みです。常に自分たちしかやっていないことを作るチャンスを探しながら経営をしています。
「面白いから──」。なぜニッチを目指すのか、その理由に隠れた櫻岡社長の価値観
――他社がやっていないことに取り組むのは、単純に経営戦略上の理由でしょうか。他にも理由があればお聞きしたいです。
戦略以上に、単純に面白いからですね。そして面白いと思えることを仕事にしていないと事業が伸びないとも思っています。
だからこそ、自分がやりたいと思うことをやってきました。かつ、ちょっと無理をしたいタイプなので、自分が確実にやれる範囲ではなく、今の自分には少し難易度が高いようなことにいつも取り組んでいます。
そしてそれで成功できたのは、ただ自分がやりたいというだけではなくて、やっぱりニッチな領域を意識したからこそだと思います。あと、ニッチすぎて誰もやっていないと、失敗しても誰も気づかないから自分自身へのダメージも少ない。事業が軌道に乗って伸びてきてはじめて知ってもらえるので、成功した部分だけを見て評価してもらえます。こんなにいいことってないですよね(笑)。

だからニッチな領域で自分のやりたいことをやっていくのが、僕にとっての正解なんです。
ニッチなことをやっていると注目されるので、名前が勝手に売れていくというメリットもあります。違う地域に営業所を出すとコストがかかりますが、ニッチなことをしていると、たとえば全国規模のメーカーの営業が自社の名前を出してくれる。他がやらないことをやることで、つながりのある人たちがオリテック21を広めてくれる状態を作れているんです。
オリテック21は多くの人に支えられており、人と人とのつながりのおかげで仕事ができています。だからこそ、オリテック21を通じて橋という人と人をつなげるものに携わるだけでなく、自分自身も人と人をつなげることを生きる目標にすると決めています。
どんな風に他者に協力できるか、反対に自分たちはどのように協力してもらえそうかを考えながら事業に取り組んでいます。
――なるほど。戦略でもあり、櫻岡さんの志向に合ったやり方でもあるんですね。
そうなんですよね。戦略的な部分を考えることも含めてすべてが面白いです。自分の戦略通りにすべてが動いていった時が一番楽しいですし、それを求めて色々なことに取り組んでいるのかもしれません。
“社員にならないような社員がほしい”。自分の色を活かして活躍できる環境
――現在採用も強化されているとのことですが、代表の櫻岡さんから見て、社員の方々にとって貴社で働くことの魅力はどこにあると思いますか。
これまで述べてきたように、当社ではニッチ戦略を取っています。そのため、他社では手にすることがないような工具や機械を使うこともあります。こうして自分たちの会社しか持っていない技術を学べる点は、やりがいにつながるのではないでしょうか。
また、極力社内で仕事を完結させる方針なので、工程管理やスケジュールの組み方といった技術以外のスキルを非常に伸ばしやすい環境でもあります。
たとえば作業の都合上、どうしても土曜日に出ないといけないことがあったとします。こうしたケースでは、原因をきちんと振り返って「どうしたら土曜日に出なくて済むのか考えて次は動いてね」と伝えています。その試行錯誤の積み重ねで、少しずつ工程管理などのスキルが伸びていく。技術力だけでなく、こうして培われたスキルも、オリテック21の利益向上を支えてくれていると感じます。
社員たち自身に自覚はないかもしれませんが、実はすごいことをやってくれているんですよね。
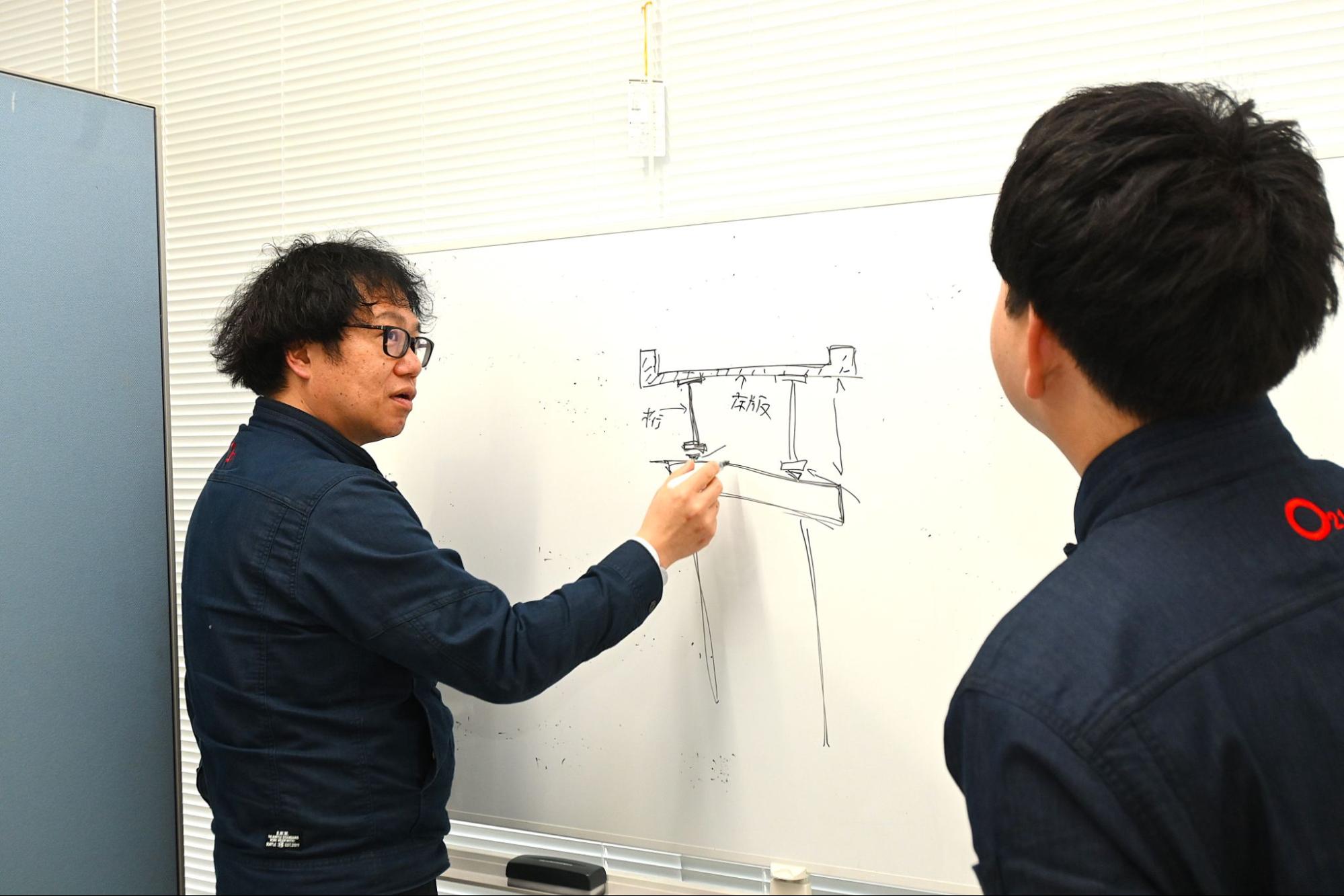
――技術力だけでなく、自分で考えて動けるビジネスパーソンとしての力も高まるわけですね。
そうだと思います。また、経営的な視点も自然と身につくのではないかと思います。
当社では、年に2回の賞与を確約してはいません。利益が出たらそれに応じて支給する形をとっています。この制度を敷いているのに、利益や売り上げがよくわからないと社員の不信感につながりますよね。そのため当社では、毎月の受注成果などの数字を社員に開示し、透明性を保っています。そして社員は、この情報や閑散期・繁忙期のことを加味して、利益、ひいては自分たちの賞与について考えています。これが社員が経営的な視点を獲得し、高い視座で仕事をすることにもつながっているように思いますね。
金銭面の制度ではこのほか、中小企業退職金共済への加入や、一部会社負担の企業型の確定拠出年金制度などがあります。
さらに時間単位の有給申請なども可能ですし、資格取得の際には受検のための旅費も含めてすべて会社支給で挑戦できるなど、手前味噌ながら福利創生も充実しているのではないでしょうか。
ちなみに資格支援に関しては、現在の支援対象は会社が決めた資格になっていますが、「この資格が必要なので、支援対象にしてください」といった意見も大歓迎です。むしろそうして積極的に学んでもらえた方がうれしいですね。
――これからのオリテック21として、どのような人材が必要だと考えていますか。
「0→1ができる人」です。僕は仕事の面白さは0を1にするところにあると思っています。だからこそ、それが得意で、今いるところから抜け出して、現在地を超えようとする感覚を持った人と一緒にやっていきたい。
独立支援なども考えているので、ゆくゆくは個人で独立したい人も大歓迎です。「0→1がしたい」という想いのある人には、社員でいてもらうより独立してもらった方が面白いですからね。矛盾していますが、その意味では、求めている人物には社員になってもらいたくないかもしれません。“社員にならないような社員がほしい”ですね。
こう考えているからには、もちろん社員には大きな裁量権を与えています。やり方は基本的に任せていますし、自分たちでやり方を考えて進めていくのは、もはやオリテック21では最低限の能力です。それだけでなく「今のやり方じゃなくてこれはどうですか」と意見をぶつけてきてくれる人が増えたらもっと面白くなりそうな予感がしています。

――最後に、オリテック21のことが気になっている候補者に一言お願いします。
社員たちのスキルは非常に伸びているので、その中に新しい社員を少しずつ入れながら、より組織を大きくし、チームとしての力量を高めていくことが今回の採用の目的です。
いきなり社員として働くのが不安だったら、最初はアルバイトからでも問題ありません。
オリテック21は会社としての色が薄い分、個々人の色が強い会社です。色の濃い個人が集まっていて、みんながそのまま集まって会社の色ができています。僕としても、「自分が赤が好きだから赤に染めよう」といった考えはまったくありません。
仕事の進め方も休み方も、どちらも自由度が高く、それぞれが自分の色のまま、いいところを発揮して成り立っています。入社後はあなたの強みを伸ばせるようにきちんとサポートするので、少しでも気になったら、ご応募いただけるとうれしいです。
株式会社オリテック21の詳細・採用情報はこちらから
求人情報:https://ort21.com/pages/99/



